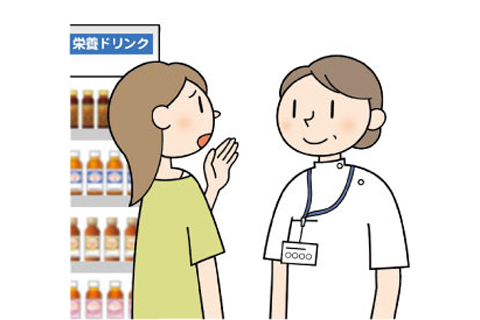暑さに負けない!家族の健康管理
夏場、特に体調に気をつけたほうがよい人は?
A. 体温調節機能が不十分な高齢者や子ども
高齢者は次のような理由で体温のコントロールができにくく、夏バテや熱中症を引き起こしやすい傾向があります。
●体温調節機能の低下……加齢により汗腺が小さくなり、汗が出にくくなる。また、皮膚に運ばれる血液量も減少し、放熱作用が弱まることが原因で熱を体内にため込みやすい。
●体内の水分量の減少……通常、成人の体内水分量は体重の60パーセントだが、高齢者は50パーセント程度まで減少する。そのため、少ない汗でも脱水症状を起こしやすくなる。
●温度感受性が鈍る……皮膚の温度センサーが衰え、暑さを感じにくくなる。
●口渇感が起こりにくい……脳での察知能力低下により、のどの渇きを感じにくくなる。
さらに、高齢者はもともと腎臓や心臓などに基礎疾患があったり、疾患はなくても体全体の機能が低下しているために重症化しやすくなります。
一方、子どもも夏場には注意が必要です。子どもは汗腺が未発達で小さく、汗を出す量が少ない分、体温調節を皮膚からの熱放散に頼る傾向があります。ところが気温が皮膚温よりも高くなると、この機能では熱を放散できないため、汗腺の未発達な子どもの深部体温は大きく上昇してしまいます。子どもが顔を赤くしていたり、よく汗をかいているときには、かなり体温が上昇していると捉えるべきです。
子どもは、体重の割に体表面積が大きいため、暑い環境では大人以上に熱を取り込みやすく、体温調節が苦手になることをしっかりと覚えておきましょう。また、小学校低学年までの子どもは衣服の調節を自ら積極的に行わないことなどもふまえ、大人がサポートしてあげることが大切です。
そのほか太っている人、胃腸の弱い人、体力の低い人なども夏に不調を起こしやすいので、気をつけましょう。
夏に不調を起こしやすい人の特徴
-
太っている人

-
体調の悪い人

-
体力の低い人

-
運動しない人

-
胃腸の弱い人

高齢者は暑さに対する自覚症状が鈍る





子どもは熱しやすく冷めやすい

-
汗腺が未発達。汗の量が少ない。

-
体重当たりの体表面積が大きく、熱を取り込みやすい。

-
環境に応じた衣服の調節が苦手。

熱中症ってどうしてなるの?
A. 高温多湿などが原因で発症しやすくなります
熱中症は体温が著しく高くなることで起こる症状で、その重症度によって3つに区分されます(下図参照)。疑われる症状が見られた場合、適切な処置を行わないと死に至る危険もあるので、本人だけでなく、周囲の人も体調の変化に気付いてあげることが大切です。
これらの症状は、特に高温多湿、風が弱い、日差しが強い日に多く発症します。また、まだ暑さに体が慣れていない夏の始めなどにも起こります。
熱中症はこうした環境のもと、次の原因で発症します。
●体温調節システムの破綻……気温が皮膚温よりも高くなると皮膚から体内の熱を逃せなくなる。皮膚表面に血液が集中する状態が続くと、脳や心臓に運ばれる血液量の確保が難しくなる。
●多量の発汗……体内の水分が減少し、脱水症状を引き起こすほか、体内の塩分バランスが崩れる。さらに体内の水分が一定量を下回ると汗が出にくくなり、体温がどんどん上昇する。
環境要因以外にも、特に、次の人はかかりやすいので注意が必要です。
●高齢者や子どもをはじめ、Q7に該当する人。
●下痢などを起こしやすく、脱水症状のある人。
●心臓病、糖尿病、皮膚疾患など基礎疾患のある人。
●利尿作用のある薬(血圧降下剤など)を服用している人。
熱中症の主な症状と対策


熱中症予防のポイント
熱中症は適切な予防法を知っていれば十分に防ぐことができます。特に高齢者や子どもなどは、周囲の人がサポートするようにしましょう。
●発症しやすい日の外出や運動を避ける。
●日傘や帽子などで直射日光に当たらないようにする。
●家では風通しをよくし、エアコンを上手に活用する。
●温度計を置いて気温をチェックする習慣をつける。
●こまめな水分補給。
●規則正しい生活を心がける。