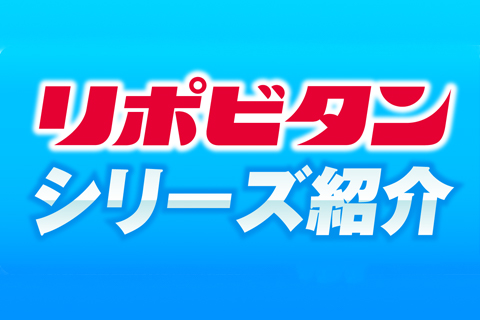積極的に治す!サヨナラ筋肉痛

運動している時は楽しくても、その後に襲ってくる筋肉痛は悩ましいもの。筋肉痛の予防には、筋肉と正しくつき合うことが第一歩。予防法のほか、筋肉痛になってしまった時の対処法もご紹介します。
筑波大学大学院人間総合科学研究科
スポーツ医学専攻教授
宮川俊平 先生

みやかわ・しゅんぺい 医学博士。1980年筑波大学医学専門学群卒業。静岡厚生病院医療技術職員、国立相模原病院厚生技官、筑波大学附属病院医員、筑波メディカルセンター病院整形外科診療科長を経て、筑波大学、同大学院で教鞭をとり、07年筑波大学大学院人間総合科学研究科教授に、11年筑波大学体育系教授に就任。
鍛えられる筋肉と
鍛えられない筋肉がある
高齢化が進む中で近年問題視され始めたのが、骨や筋肉、関節などの運動器の障害により介護リスクを高める「ロコモティブシンドローム」※1と、加齢により筋肉の量や筋力が減少する「サルコペニア」※2。これは高齢者だけの問題ではなく、運動不足になっている現代人への警鐘ともいえます。
確かに日常のどんな動作でも筋肉は使っています。けれども、意識して動かすことはあまりありません。まずは筋肉のことを正しく理解するところから始めましょう。
私たちの体をつくっている筋肉には「骨格筋」、「心筋」、「平滑(へいかつ)筋」の3種類があります。骨格筋は体を動かすのに必要な筋肉で、足や腕の筋肉などがこれ。運動などで鍛えて増やせる唯一の筋肉です。自分の意思で動かせる筋肉なので「随意(ずいい)筋」と呼ばれます。一般に「筋肉」というと、この骨格筋のことです。
心筋はその名の通り、心臓の筋肉のこと。そして平滑筋は、胃や腸などの心臓以外の内臓の壁にある筋肉です。心筋と平滑筋は鍛えることができません。また、自分の意思では動かせないために、「不随意筋」と呼ばれています。
鍛えるべきは
筋肉のキモ「骨格筋」
私たちは骨格筋が生み出した力を動力源として、様々な身体運動を行っています。その骨格筋は2種類の筋線維によって形成されています。1つは収縮するスピードが速く、瞬発力を生む「速筋」。もう1つは収縮するスピードは遅いけれど、長く継続的な力を生むことができる「遅筋(ちきん)」です。役割の異なるこれらの筋線維のおかげで、瞬発的な力が出せたり、持続的な運動をしたりできるのです。骨格筋は、体を動かす役割の他にも、次のような役割を担っています。
- 関節を安定させ、姿勢を保つ。
- 外的な衝撃から、内臓や血管などの体の組織を守る。
- 収縮することで、体温維持のための熱源となる。
- 収縮することで血管を圧迫し、血液循環をサポートする。
- 動かすことで脂肪を運動エネルギーとして使い、糖や脂質の代謝を一定に保つ。
骨格筋が筋肉全体に占める割合は約4割。骨格筋を鍛えることは、体の様々な機能を維持する上でも、とても有効なことです。筋肉痛への対処法も心得て、無理をすることなく、筋肉を鍛えていきましょう。
※1運動器症候群:骨や関節の病気、筋力やバランス能力の低下によって転倒や骨折をしやすくなり、介護が必要となるリスクが高い状態のこと。
※2加齢性筋肉減弱症:加齢に伴って、筋肉の量や筋力が減少していく現象で、ギリシア語の「サルコ(筋肉)」と「ペニア(減少)」を組み合わせた造語。

骨格筋はこうして成り立っている!
骨格筋は、筋線維と呼ばれる直径0.1mm前後の円柱状の細長い細胞の集まりです。筋線維が筋内膜によって束ねられたものが筋線維束と呼ばれ、それがさらに束ねられて筋上膜で覆われ、1つの筋肉を構成しています。このように筋肉は、層状の構造になっていることにより、強度を保っています。